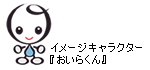幼児教育・保育の無償化
令和元年10月1日から幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する児童の利用料が無償化されました。
施設・サービスの種類により、対象年齢、上限額、必要な手続きなどが異なりますので、詳しくはご利用している(もしくはご利用になる)施設・サービス別の案内をご確認ください。
幼稚園、認定こども園(教育1号認定)を利用している児童
保育料の無償化
幼稚園、認定こども園(教育1号認定)の児童について、満3歳から5歳までの保育料が無償となります。
必要な手続き
新たに、手続きを行う必要はありません。
無償化の対象とならないもの
通園送迎費、食材料費、行事費などの施設が実費徴収しているものについては、ご負担していただきます。
※ただし、食材料費のうち副食費(おかず・おやつ等に係る費用)については、以下に該当する場合に限り免除となります。
- 年収360万円未満相当世帯の児童
- 小学校3年生までの子どもから数えて第3子以降の児童
- 18歳以下の子どもから数えて第3子以降の児童(町独自施策:上限4,700円)
預かり保育利用料の無償化
4月1日時点で3歳から5歳の児童であり、町から保育の必要性の認定を受けた場合は、預かり保育の利用料も無償化の対象となります。
満3歳(4月1日時点で2歳)の児童については、住民税非課税世帯で、なおかつ町から保育の必要性の認定を受けた場合のみが無償化の対象となります。
無償化の上限額
預かり保育の無償化の上限金額は以下のとおりとなります。
- 4月1日時点で3歳から5歳の児童:「月額11,300円」と「月の利用日数×450円」のいずれか少ない額が、無償化の月額上限額となります。
- 満3歳(4月1日時点で2歳)の児童:「月額16,300円」と「月の利用日数×450円」のいずれか少ない額が、無償化の月額上限額となります。
必要な手続き
- 事前に町の認定を受ける必要がありますので、『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)』を作成し、入園先の施設へ提出してください。
- 保育を必要とする理由について確認する必要があるので、『保育の理由について確認できる書類(就労証明書など)』を申請書と併せて提出してください。
保育を必要とする理由(認定要件) [PDFファイル/171KB]
※保護者に保育を必要とする理由がない場合は、認定を受けることができません。
※『申請書』及び『保育の理由について確認できる書類』の様式は、このページ下部にてダウンロードできますので、必要に応じてご利用ください。
保育所、認定こども園(保育2・3号認定)を利用している児童
保育料の無償化
2号認定(4月1日時点で3歳から5歳児)を受けて保育施設を利用する児童について、保育料が無償となります。
3号認定(0歳から2歳の児童)についても、町民税非課税世帯を対象に、保育料が無償となります。
必要な手続き
新たに、手続きを行う必要はありません。
無償化の対象とならないもの
◆通園送迎費、食材料費、行事費などの施設が実費徴収しているものについては、ご負担していただきます。
※ただし、食材料費のうち副食費(おかず・おやつ等に係る費用)については、以下に該当する場合に限り免除となります。
- 年収360万円未満相当世帯の児童
- 小学校3年生までの子どもから数えて第3子以降の児童
- 18歳以下の子どもから数えて第3子以降の児童(町独自施策:上限4,700円)
◆延長保育の利用料は、無償化の対象外となります。
幼稚園(就園奨励費対象施設)を利用している児童
保育料の無償化
幼稚園(就園奨励費対象施設)の児童について、満3歳から5歳までの保育料が無償となります。
また、入園料は入園初年度に限り月割り(入園料÷初年度の在籍月数)を行い、無償化の対象とします。
無償化の上限額
月割りの入園料と毎月の保育料を合わせ、月額25,700円(上限)までが無償化の対象となります。
必要な手続き
事前に町の認定を受ける必要がありますので、『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)』を作成し、入園先の施設へ提出してください。
※預かり保育利用料の無償化の対象となる児童で、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2・3号)」を提出し、町から保育の必要性の認定を受けた場合は、この申請書の提出は必要ありません。
※『申請書』の様式は、このページ下部にてダウンロードできますので、必要に応じてご利用ください。
無償化の対象とならないもの
通園送迎費、食材料費、行事費などの施設が実費徴収しているものについては、ご負担していただきます。
預かり保育利用料の無償化
4月1日時点で3歳から5歳の児童であり、町から保育の必要性の認定を受けた場合は、預かり保育の利用料も無償化の対象となります。
満3歳(4月1日時点で2歳)の児童については、住民税非課税世帯で、なおかつ町から保育の必要性の認定を受けた場合のみが無償化の対象となります。
無償化の上限額
預かり保育の無償化の上限金額は以下のとおりです。
- 4月1日時点で3歳から5歳の児童:「月額11,300円」と「月の利用日数×450円」のいずれか少ない額が、無償化の月額上限額となります。
- 満3歳(4月1日時点で2歳)の児童:「月額16,300円」と「月の利用日数×450円」のいずれか少ない額が、無償化の月額上限額となります。
必要な手続き
- 事前に町の認定を受ける必要がありますので、『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)』を作成し、入園先の施設へ提出してください。
- 保育を必要とする理由について確認する必要があるので、『理由を確認できる書類(就労証明書など)』を申請書と併せて提出してください。
保育を必要とする理由(認定要件) [PDFファイル/171KB]
※保護者に保育を必要とする理由がない場合は、認定を受けることができません。
※『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)』を提出し、町から保育の必要性の認定を受けた場合は、、『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)』の提出は必要ありません。
※『申請書』及び『保育の理由について確認できる書類』の様式は、このページ下部にてダウンロードできますので、必要に応じてご利用ください。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンターを利用している児童
利用料の無償化
4月1日時点で3歳から5歳の児童であり、町から保育の必要性の認定を受けた場合は、利用料の無償化の対象となります。
満3歳(4月1日時点で2歳)の児童については、住民税非課税世帯で、なおかつ町から保育の必要性の認定を受けた場合のみが無償化の対象となります。
無償化の上限額
利用料の無償化の上限金額は以下のとおりとなります。
- 4月1日時点で3歳から5歳の児童:「月額37,000円」が、無償化の上限額となります。
- 満3歳(4月1日時点で2歳)の児童:「月額42,000円」が、無償化の上限額となります。
必要な手続き
- 事前に町の認定を受ける必要がありますので、『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)』を作成し、保健こども課へ提出してください。
- 保育を必要とする理由について確認する必要があるので、『理由を確認できる書類(就労証明書など)』を申請書と併せて提出してください。
保育を必要とする理由(認定要件) [PDFファイル/171KB]
※保護者に保育を必要とする理由がない場合は、認定を受けることができません。
※『申請書』及び『保育の理由について確認できる書類』の様式は、このページ下部にてダウンロードできますので、必要に応じてご利用ください。
『申請書』及び『保育の理由について確認できる書類』各種様式
幼稚園(就園奨励費対象施設)を利用している児童で、町から保育の必要性の認定を受けない場合
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(エクセル版) [Excelファイル/22KB]
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(PDF版) [PDFファイル/278KB]
幼稚園(就園奨励費対象施設を含む)、認定こども園(教育1号認定)を利用している児童及び認可外保育施設等を利用している児童で、町から保育の必要性の認定を受ける場合
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (エクセル版) [Excelファイル/45KB]
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDF版) [PDFファイル/532KB]
『保育を必要とする理由』と『保育の理由について確認できる書類』
『子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)』を提出する際に、添付する必要があります。
まずは、『保育を必要とする理由(認定要件)』をご確認していただき、必要な書類を準備してください。
保育を必要とする理由(認定要件) [PDFファイル/171KB]
| 保育を必要とする理由 | 保育の理由について確認できる書類 |
|---|---|
| 会社や自宅を問わず、1箇月48時間以上働いている |
○就労証明書 [Excelファイル/63KB]
|
| 出産予定・出産して間もないとき |
○母子手帳(出産予定日がわかるページ)の写し
|
| 病気や障がいのため保育が困難なとき |
○診断書(ワード版) [Wordファイル/24KB] ○障がいの認定を受けている場合は、手帳の写しまたは障がい基礎年金等の受給を証するもの(この場合は診断書不要) |
| 傷病者や障がい者を看護または介護しているとき |
○看護・介護申立書(ワード版) [Wordファイル/23KB]
|
| 大学や職業訓練校、専門学校などに通っているとき |
○在学(受講)証明書 |
| 仕事を探しているとき(求職活動) | ○求職申立書(ワード版) [Wordファイル/22KB] ○求職申立書(PDF版) [PDFファイル/111KB] |
| 火災などの災害の復旧にあったとき | ※保健こども課へお問い合わせください |
| 虐待や配偶者等からのDV(家庭内暴力)のおそれがあるとき | ※保健こども課へお問い合わせください |
| 育児休業を取得しているとき |
○就労証明書(エクセル版) [Excelファイル/64KB]
|
| 上記の他、町が認めるもの | ※保健こども課へお問い合わせください |