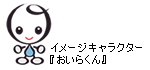令和7年度 古墳館歴史講座を開催します
おいらせ阿光坊古墳館歴史講座を開催します。
おいらせ阿光坊古墳館では令和7年度おいらせ阿光坊古墳館歴史講座を10月に開催します。
第1講座 (10月4日) は 丸山 浩治 氏
第2講座 (10月11日) は 古矢 聡江 氏(リモートでの講演)
第3講座 (10月25日) は 新井 隆一 氏
以上の方をそれぞれ講師に招きします。この機会にぜひ聴講ください。
|
日時 |
演題・概要 |
講師 |
|---|---|---|
|
10月4日(土曜日) 13時30分~15時00分
|
演題:「十和田平安噴火とおいらせの人々」 過去2000年間で国内最大級の規模だったとされる10世紀の十和田噴火、おいらせ町域にはどのような影響があったのでしょう?町内で発掘された遺跡と火山灰から、当時この地に在った人々とその後の動態について考えます。 |
岩手県立博物館 丸山 浩治 氏 |
|
10月11日(土曜日) 13時30分~15時00分 (リモート講演) |
演題:「阿光坊古墳群から見た外の世界とのつながり」 阿光坊古墳群からは土器や蕨手刀、轡、ガラス玉など様々な遺物が出土しています。これらの遺物の由来を検証することで、古墳群からみえる地域のつながりを紹介します。また考古学の成果に加え、末期古墳に関わる自然科学分析の成果の一端も紹介します。 |
パリノ・サーヴェイ株式会社 古矢 聡江 氏 |
|
10月25日(土曜日) 13時30分~15時00分 |
演題:「阿光坊古墳群と太平洋沿岸交通」 阿光坊古墳群は、関東の古墳文化の影響を受けた遺構・遺物が多く、7世紀の関東との太平洋沿岸交通の産物と考えられます。その交通の背後には、当時の倭国の権力者、蘇我氏が存在していました。その交通路は津軽海峡を越えて北海道へ伸びていました。阿光坊古墳群の被葬者は、太平洋沿岸を南北につなぐ交易を掌るリーダーとみることができます。今回は上記の内容をまとめて解説します。 |
教育出版株式会社 新井 隆一 氏 |
要予約(電話、窓口にて承っております)
場所:おいらせ阿光坊古墳館 体験学習室
住所:青森県上北郡おいらせ町阿光坊107-4
☎:0178-20-0405 📠:0178-20-0465
※定員40人(要予約)