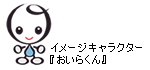国民健康保険について
国民健康保険は、被保険者の皆さまが保険税を負担し、安心してお医者さんにかかることができるよう、いざというときの負担を軽くする社会保障制度です。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、必ず国保に加入します。外国人登録をしていて1年以上日本に滞在すると認められた外国人も国保に加入しなければなりません。
国保に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に必ず届け出を行いましょう。加入の届け出が遅れると、保険税は加入の資格を得た日まで、さかのぼって納めなければなりません。その間にかかった医療費は全額自己負担となる場合があります。また、脱退する届け出が遅れると、保険税が二重払いになる場合がありますので、ご注意ください。
届け出について
- 受付窓口:役場本庁舎1階 3番窓口 健康保険課
加入するとき
他の市区町村から転入したとき
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)
職場の健康保険をやめたとき(被扶養者からはずれたとき)
- 職場の健康保険をやめた(被扶養者に該当しなくなった)日がわかる証明書(資格喪失証明書等)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)
生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)
脱退するとき
他の市区町村へ転出するとき
- 国民健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)
職場の健康保険に加入したとき(被扶養者になったとき)
- 国民健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
- 加入した健康保険の加入日がわかるもの「資格情報のお知らせ」または「資格確認書等」
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)
生活保護を受けるようになったとき
- 国民健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
- 保護開始決定通知書
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)
その他
住所、氏名、世帯主が変わったとき
- 国民健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)
世帯を分けたとき、一緒にしたとき
- 国民健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)
国保の資格情報のお知らせ・資格確認書をなくしたとき
- 健康保険課で再交付の申請手続きをしてください。
就学により転出するとき(学生用国保の交付)
- 国民健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
- 在学証明書など
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 窓口に来た人の身分証明書(運転免許証など)
※ 就学を終えたら、その旨の届け出も必要です。
病院に行くときは、忘れずに「マイナ保険証(マイナンバーカード)」または「資格確認書」を提示しましょう。
- 提示することにより、下記の自己負担割合分のみのお支払いで治療やお薬などの医療給付が受けられます。
お医者さんにかかるとき
| 小学校就学前 | 2割 |
|---|---|
| 小学校~70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上 | 2割 |
| 〃 (現役並み所得者) | 3割 |
※ 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までの期間に、「資格確認書兼高齢受給者証または、
お知らせ」が交付されます。自己負担割合は2割(現役並み所得者は3割)です。(所得による負担区分判定の更新時期は8月です。)
※ 75歳の誕生日に、「国保」から「後期高齢者医療制度」に移行となります。
いろいろな給付
療養費
- 医療費をいったん全額自己負担し、健康保険課へ申請後、審査決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。
- 急病などの緊急やむを得ず、「マイナ保険証(マイナンバーカード)」または「資格確認書」の提示ができずに治療を受けたとき
- お医者さんが治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき
- お医者さんが必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外旅行中の急な診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
移送費
- お医者さんの指示により、緊急やむを得ず、重病人の入院や転院などの移送費がかかったとき、申請して必要と認められた場合に支給されます。
妊産婦十割給付
- 病院等から出産予定日が確認できるもの(母子手帳等)をお持ちになり、申請してください。申請した日から出産日の翌月末まで、外来療養の給付を受けることができます。受診の際は、「マイナ保険証(マイナンバーカード)」または「資格確認書」と一緒に提示ください。
出産育児一時金
- 出産育児一時金の支給被保険者が出産したときに、申請により支給されます。原則として国保から医療機関などに直接支払われます。なお、妊娠12週以降の死産や流産でも支給されます。
| 産科医療保障制度等に加入している医療機関での出産 | 50万円 |
| 産科医療保障制度等に加入していない医療機関での出産 | 48万8千円 |
- 直接支払制度のご利用は、病院などへお申し込みください。
- 出産費用が支給額未満だった場合、申請すれば世帯主に差額支給されます。
- 出産費用をいったん全額お支払した人は、申請により世帯主に支給されます。
- 分娩者が以前会社の健康保険の「本人」で1年以上加入しており、資格喪失後6ヵ月以内の出産は、前の会社の健康保険から支給されます。(国保からは支給されません。)
葬祭費
- 被保険者が亡くなったとき申請により、葬祭を行った人に50,000円支給されます。
交通事故などにあったとき
- 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、届け出により国保で治療を受けることができます。ただし、加害者から治療費を受け取りったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますので、必ず国保にご相談ください。
保険証等が使えないとき
- 仕事上のけがなどは、労災保険の対象となります。
- 故意の犯罪行為・事故、けんかや泥酔による傷病については、国保の給付が制限されることがあります
保険税は国保を支える大切な財源です。納期内に必ず納めましょう。
- 保険税を滞納すると、医療費をいったん全額自己負担することになる場合や、入院時の高額療養費の「限度額適用認定」を受けられない場合があります。
- 国保被保険者全員が65~75歳未満の世帯の保険税は原則として年金からの天引きとなります。ただし、年金から天引きとなる人でも、保険料の未納がない場合、申出により口座振替できます。
- 保険税の納付を口座振替にすると、納め忘れの心配がなくなります。納税通知書と通帳、届け出印をお持ちになり、町指定の金融機関で申し込みできます。
- 特別な事情で保険税を納めることが難しいときは、お早めに税務課へご相談ください。
※ 国民健康保険税に関する詳しい内容については、税務課(直通Tel:0178-56-4704)へお問い合わせください。