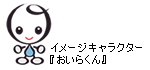国民健康保険税とは
子ども・子育て支援金制度が始まります
令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まり、支援金を国民健康保険税とあわせて拠出いただきます。詳細は子ども家庭庁リーフレットをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度リーフレット(子ども家庭庁) [PDFファイル/1.74MB]
国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険の運営を支える重要な財源です。国民健康保険に加入している方には、「給付を受ける権利」があるのと同時に、「国民健康保険税を支払う義務」があります。
納税義務者
国民健康保険税は、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、課せられます。(地方税法第703条の4及び国民健康保険税条例第1条の規定による)
世帯主が国民健康保険の被保険者でなくとも、世帯員のなかに国民健康保険の被保険者がいる場合は世帯主に対して課税されます。(擬制世帯主制度)
この場合、擬制世帯主の所得は保険料算定に含みません。ただし、軽減判定の算定には含まれます。
令和7年度税率と計算方法
国民健康保険税は次の内訳毎に、下記に記載した3項目を計算し、その合計額を各世帯で負担していただきます。
内訳
- 医療保険分:国民健康保険制度の運営に充てられるものです
- 後期高齢者支援分:後期高齢者医療制度を現役世代で支えるためのものです
- 介護保険分:介護保険制度の運営に充てられるものです
※介護保険分を負担するのは、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の方のみです。
|
算定項目 |
医療保険分 |
後期高齢者支援分 |
介護保険分 |
|---|---|---|---|
| 所得割額 | 7.45% | 2.7% | 2.3% |
| 均等割額 | 31,600円 | 11,400円 | 13,800円 |
| 平等割額 | 21,600円 | 7,800円 | 6,800円 |
※令和6年度までは所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の4項目で計算する4方式を採用していましたが、県の指針に基づき令和7年度からは資産割額を廃止し、所得割額、均等割額、平等割額の3項目で計算する3方式に変更しました。また、併せて税率も変更しました。
計算方法
【医療保険分】 ※課税限度額66万円(最高年額)
- 所得割額:(前年中の合計所得金額-基礎控除額43万円)☓7.45%
- 均等割額:国保に加入している人数☓31,600円
- 平等割額:1世帯につき21,600円
医療保険分年税額=1+2+3・・・A
【後期高齢者支援分】 ※課税限度額26万円(最高年額)
- 所得割額:(前年中の合計所得金額-基礎控除額43万円)☓2.7%
- 均等割額:国保に加入している人数☓11,400円
- 平等割額:1世帯につき7,800円
後期高齢者支援分年税額=1+2+3・・・B
【介護保険分】 ※課税限度額17万円(最高年額)
- 所得割額:(前年中の合計所得金額-基礎控除額43万円)☓2.3%
- 均等割額:国保に加入している人数☓13,800円
- 平等割額:1世帯につき6,800円
介護保険分年税額=1+2+3・・・C
- 介護保険第2号被保険者のいない世帯は、A(医療保険分)+B(後期高齢者支援分)となります。
- 介護保険第2号被保険者のいる世帯は、A(医療保険分)+B(後期高齢者支援分)+C(介護保険分)となります。
※介護保険第2号被保険者とは、40歳から64歳までの方です。
均等割・平等割の軽減措置
1)世帯の前年の合計所得が、下表の基準に該当する場合、軽減割合に応じて均等割額と平等割額が減額されます。
※世帯の中の被保険者が後期高齢者医療制度に移行しても継続してその世帯員である場合は、移行した方(特定同一世帯所属者)を含めて、軽減判定を行います。
ただし、世帯主が変わると、その月から世帯主と被保険者のみで軽減判定を行います。
| 軽減割合 | 世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の合計所得金額 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+30.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+56.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下 |
2)世帯の中の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被保険者が1人になる世帯については、医療分・後期高齢者支援分に係る平等割額が移行後5年間は2分の1、その後3年間は4分の1減額されます。
ただし、年度途中で世帯に新しい被保険者が出たときは次の年度から、世帯主が変わったときはその月から、平等割額減額の適用はなくなります。
3)未就学児(6歳に達する日以降の3月31日までにある方)は均等割が半額となります。
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置
非自発的な失業のため職場の健康保険を脱退し、国民健康保険に加入することになった方に対する保険税の軽減措置制度があります。
対象となる方
対象となるのは、次の2つの項目いずれにも該当する方です。
- 離職時点で65歳未満の人
- 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である人
| 対象となる理由コード | 離職理由 |
|---|---|
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 対象となる理由コード | 離職理由 |
|---|---|
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
軽減期間
軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間となります。ただし、就職等で他の保険に加入した場合は、その時点までとなります。
| 離職年月日 | 軽減期間 |
|---|---|
| 令和6年12月15日 | 令和6年12月から令和8年3月まで |
| 令和7年 3月31日 | 令和7年 4月から令和9年3月まで |
軽減内容
国民健康保険税の所得割額を算定する際、離職した日の翌日から翌年度末までの間、非自発的失業者の方の給与所得を30/100として算定します。※軽減対象となるのは、給与所得のみです。
申告方法
次のものをお持ちになり、税務課(本庁舎)で非自発的失業者である旨、申告してください。対象となる要件に該当する方でも、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」がない場合は申告を受け付けすることができません。
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」 ※ただし、(仮)と記載があるものは不可
- はんこ ※認印可、シャチハタ等スタンプ印は不可
産前産後期間に係る国保税の軽減措置
令和6年1月1日から、 出産される国民健康保険被保険者の保険税の軽減措置が開始されました。
対象となる方
出産予定のまたは出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
軽減期間
出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4ヶ月相当分が減額対象期間となります。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの6ヶ月相当分が減額対象期間となります。
軽減内容
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額が対象期間分減額されます。
届出方法
次のものをお持ちになり、税務課(本庁舎)へ届出してください(郵送での届出も可)。届出は出産予定日の6ヶ月前からすることができます(出産後の届出も可能です)。
- 産前産後期間に係る保険税軽減届書 [PDFファイル/207KB]
- 出産予定日を確認することができる書類(母子健康手帳の表紙と出産予定日が分かるページの写し)
※多胎妊娠の場合はその旨を確認することができる書類が必要です(それぞれの母子健康手帳の写し)。
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
保険税の納期限(普通徴収)
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
保険税の納付相談
国民健康保険税の納付が困難な方のために、納付相談を実施しております。お気軽にお問い合わせください。